- 毎晩ベッドに入っても、なかなか寝つきが悪くて困っている
- 寝る時間になるといろいろ考え事が浮かんできて眠れない
- 寝つきが悪い原因が何なのかわからず悩んでいる
- 急に寝つきが悪くなった理由を知りたい
- 生まれつき寝つきが悪い体質なのか、改善できるのか知りたい
こんな悩みがありませんか?
 編集部
編集部夜になると頭が冴えてきて、いろいろな考え事が浮かんできて眠れません。布団に入るとストレスや不安が襲ってきて、気づけば何時間も経ってしまいます。
寝つきが悪いと、翌日の疲労感や集中力低下につながるだけでなく、長期的には健康にも悪影響を及ぼします。特に「眠らなければ」という焦りが強くなるほど、余計に眠れなくなるという悪循環に陥りがちです。
この記事では寝つきが悪い人の特徴やその原因から、急に寝られなくなった時の対処法、そして生まれつき寝つきが悪い人のための習慣改善法まで詳しく解説します。
- 寝つきが悪くなる原因と特徴的な思考パターン
- すぐに実践できる即効性のある対処法
- 根本的な睡眠の質を改善するための生活習慣
寝つきの悪さには様々な原因があり、その原因に合わせた対策を行うことで大幅に改善できます。ストレスや考え事で眠れない夜も、適切な呼吸法やツボ押しで対処できるようになります。
あなたも今夜から実践できる対策で、スッと眠りにつける心地よい睡眠を取り戻しましょう。
寝つきが悪い人の3つの特徴と原因
寝つきが悪い人には、実はいくつかの共通する特徴があります。



寝つきの悪さには明確な理由があります!
それぞれ解説していきます。
眠ろうとするほど頭が冴えてしまう
眠りたいと強く思えば思うほど、逆に頭が冴えてしまうことがあります。
これは「眠らなければ」という焦りが交感神経を活発にして、目が冴えてしまう悪循環を引き起こすためです。
実際に、なかなか眠れないと焦りを感じている人は以下のような状態になりがちです。
- 眠れないことへの不安が強くなる
- 時計を何度も見てしまう
- 体がリラックスできない
眠ろうとするほど頭が冴えてしまうのは、自律神経の働きが関係しています。
睡眠には副交感神経の働きが重要ですが、焦りは交感神経を優位にしてしまいます。
無理に眠ろうとせず、「眠れなくてもいいや」くらいの気持ちでいると案外眠れるものですよ。
いろいろ考えすぎて眠れない状態に陥る
ベッドに入ると、急に様々な考えが頭をめぐり始めることがあります。
暗い場所で横になると、脳が外部からの刺激が少なくなるため、内側に意識が向かいやすくなり、考えが止まらなくなりやすいのです。
次のような考えが浮かんでくると、なかなか眠れなくなってしまいます。
- 明日の予定や心配事
- 過去の失敗や後悔
- 解決策が見つからない問題
- 人間関係の悩み
こうした考え事は、布団から出られない原因にもなります。


寝る前に考え事ノートを用意して、気になることを書き出すと頭の中がすっきりするでしょう。
明日解決できることは明日に回して、今は睡眠を優先する気持ちが大切です。
ストレスや緊張で自律神経のバランスが崩れる
ストレスや緊張が続くと、自律神経のバランスが崩れて寝つきが悪くなります。
自律神経は交感神経と副交感神経のバランスによって調整されており、ストレスが多いと交感神経が優位になりやすく、リラックスできない状態が続きます。
以下のような状態は自律神経のバランスを崩す原因となっています。
- 仕事や人間関係のストレス
- 生活リズムの乱れ
- 寝る直前までのスマホ使用
- 運動不足
自律神経のバランスを整えるためには、日常生活の見直しが必要です。
ぐっすり眠る方法として、入浴やリラックス法を取り入れるのが効果的です。
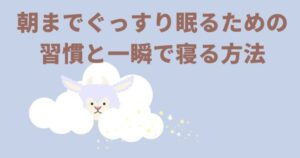
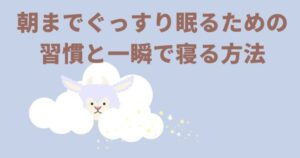
睡眠前の習慣を見直して、リラックスできる時間を持つようにしましょうね。
急に寝つきが悪くなった時の4つの対処法
急に寝つきが悪くなってしまったときには、すぐに実践できる対処法があります。



焦らず試してみてくださいね!
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ベッドから一度離れて気分をリセットする
なかなか眠れないときは、いったんベッドから離れるのが効果的です。
ベッドで眠れない時間が長く続くと、脳が「ベッド=眠れない場所」と認識してしまい、さらに寝つきが悪くなる悪循環に陥ることがあります。
下記のような方法でベッドから離れて気分をリセットしてみましょう。
- 明かりを暗めにした部屋で過ごす
- 退屈な本を読む
- 軽いストレッチをする
ただし、スマホやパソコンの使用は青色光の影響で逆効果になります。
また、カフェインで眠くなるという人もいますが、基本的に寝る前のカフェイン摂取も避けましょう。


眠気を感じたらベッドに戻るという、気軽な気持ちで試してみるといいですよ。
リラックスできる腹式呼吸を行う
腹式呼吸はリラックス効果があり、副交感神経を活性化させます。
ゆっくりとした深い呼吸は、緊張状態から解放され、自然な眠りへと導いてくれる効果があるのです。
腹式呼吸は以下の手順で簡単に行うことができます。
- 仰向けになりリラックスした姿勢をとる
- 口から大きく息を吐き出す
- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませる
- 吸う時間の2倍かけてゆっくり口から息を吐く
腹式呼吸を行うことで、酸素の供給が増え体がリラックスします。
呼吸に集中することで、雑念が減り、心を落ち着かせる効果も期待できます。
息を吐くときは、嫌なことも一緒に吐き出すイメージを持つとさらに効果的ですよ。
体の力を抜く筋弛緩法を試みる
筋弛緩法は、意識的に筋肉の緊張と弛緩を繰り返す方法です。
最初に筋肉に力を入れて緊張させた後、脱力することで、よりリラックス効果を高めることができます。
筋弛緩法は次のような手順で行います。
- 手をグーに握り5秒間力を入れる
- 一気に力を抜いて10秒間リラックス
- 足首を曲げて5秒間力を入れる
- 力を抜いて10秒間リラックス
筋弛緩法は体全体の緊張をほぐすのに役立ちます。
特に寝る前に体の緊張状態に気づかないことも多いので、意識的に力を抜くことが重要です。
力を入れる部分を変えながら全身に行うと、体の緊張が溶けていくのを実感できますよ。
百会のツボを優しく押す
頭頂部にある「百会」というツボは、心を落ち着かせる効果があります。
百会は頭のてっぺんにあるツボで、精神を安定させ、気持ちを落ち着かせる働きがあるとされています。
百会のツボは以下の方法で刺激するといいでしょう。
- 両手の指先を頭頂部に当てる
- 息を吐きながら5秒ほどかけて優しく押す
- 軽く息を吸い、また押す
- これを数回繰り返す
百会のツボ押しは、精神的な高ぶりを鎮める効果があります。
強く押さずに、心地よく感じる程度の力加減で行うことが大切です。
ツボ押しと一緒に深呼吸をすると、さらにリラックス効果が高まりますよ。
強く押しすぎないこと
生まれつき寝つきが悪い人が実践すべき3つの習慣
生まれつき寝つきが悪いと感じている人でも、習慣を変えることで改善できます。



継続が鍵です!習慣化していきましょう
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
毎日同じ時間に起きて体内リズムを整える
規則正しい生活リズムは、良質な睡眠の基本となります。
特に起床時間を一定にすることは、体内時計をリセットする重要な合図となり、夜の睡眠の質を高める効果があります。
体内リズムを整えるために以下のポイントを実践してみましょう。
- 休日も平日と同じ時間に起きる
- 朝日を浴びて体内時計をリセット
- 就寝時間より起床時間を優先する
朝起きる時間が一定だと、体は自然と眠りに向かう準備を始めます。
特に日光を浴びることでセロトニンが分泌され、夜のメラトニン産生にも影響します。


休日だからといって寝坊すると、体内リズムが乱れてしまうので注意しましょうね。
就寝前のカフェインやニコチン摂取を避ける
カフェインやニコチンには覚醒作用があり、寝つきを妨げます。
カフェインは体内で分解されるまでに約5〜6時間かかるため、昼過ぎ以降の摂取は夜の睡眠に影響する可能性があります。
カフェインやニコチンの摂取について次のことに気をつけましょう。
- 午後以降はカフェイン摂取を控える
- 緑茶やチョコレートにもカフェインがあることを意識
- 寝る前の喫煙は避ける
カフェインに敏感な人は、午後からはハーブティーなどに切り替えるといいでしょう。
また、快眠ココアなど、睡眠を促す飲み物を選ぶのもおすすめです。


就寝前の習慣を見直して、良質な睡眠のための準備をしてくださいね。
日中の適度な活動量を確保する
日中に適度な活動をすることで、夜の睡眠の質が高まります。
身体活動は疲労物質を蓄積させ、自然な眠気を促す効果があるため、寝つきの改善に役立ちます。
適度な活動量を確保するために以下の取り組みを実践しましょう。
- 日中に30分以上の運動を取り入れる
- デスクワークの合間に立ち上がる
- エレベーターより階段を使う
運動は筋トレと睡眠のように激しいものでなくても効果があります。


ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を活性化させるので避けましょう。
軽いストレッチや散歩など、日常生活に取り入れやすい運動から始めてみるといいですよ。
眠れないまま朝になった時の対処時間別ガイド
眠れないまま朝を迎えてしまった場合でも、一日を乗り切る方法があります。



一晩眠れなくても工夫次第で乗り切れます!
それぞれの対処法を詳しく見ていきましょう。
横になるだけでも休息になることを理解する
眠れなくても横になるだけで体は一定の休息を得ています。
完全に眠れなかったとしても、横になって目を閉じることで、筋肉の緊張が緩和され、身体的な回復が得られます。
横になって休息を取るときは次のことを意識するといいでしょう。
- 眠れなくても自分を責めない
- 「休息」と「睡眠」は別物と考える
- リラックスした状態を維持する
眠れなかったと思うと不安になりますが、実際は思っているより眠れています。
眠りが浅い原因を気にしすぎると、かえって次の夜も眠れなくなります。


一晩眠れなくても大丈夫、と気楽に考えることも大切な対処法ですよ。
軽い活動で一日のスタートを切る
眠れなかった翌朝は、軽い活動から始めることで体を目覚めさせましょう。
朝日を浴びることで体内時計をリセットし、セロトニンの分泌を促すことで覚醒を助けます。
朝のスタートに役立つ活動として以下のことを試してみてください。
- 朝日を浴びる
- 水分をしっかり摂る
- 軽いストレッチをする
- 深呼吸で体を活性化させる
睡眠不足の日は無理な予定を入れず、できるだけ負担の少ない活動を選びましょう。
カフェインに頼るよりも、眠気に効くツボを押すなどの自然な方法を試すといいです。


翌日の生活リズムを整えるために、決まった時間に起きることを心がけましょうね。
昼寝は15分以内に抑える
眠れなかった日の昼寝は15分以内に抑えることが重要です。
長時間の昼寝をすると夜の睡眠に影響し、さらに睡眠リズムが乱れる原因になります。
効果的な昼寝のポイントは以下の通りです。
- 15分以内の短時間に限定する
- 午後早めの時間帯に行う
- タイマーをセットする
- 起きたらすぐに体を動かす
短時間の昼寝は疲労回復に効果的ですが、長すぎると深い眠りに入ってしまいます。
昼寝の後は水を飲んだり顔を洗ったりして、しっかり目を覚ましましょう。
短時間で睡眠をとるコツを知っておくと、効率よく回復できますよ。


ストレスが原因の寝つきの悪さを改善する5つの方法
ストレスは寝つきの悪さの大きな原因のひとつです。



ストレスケアが睡眠の質を大きく左右します!
それぞれの方法について解説していきます。
寝る前に「考え事ノート」に不安を書き出す
寝る前に考え事が頭から離れないときは、ノートに書き出すことが効果的です。
考え事ノートに不安や心配事を書き出すことで、頭の中がすっきりし、脳が休息モードに入りやすくなります。
考え事ノートの使い方は以下のように実践してみましょう。
- 寝る30分前に思いつく心配事をすべて書き出す
- 翌日のやるべきことをリスト化する
- 解決策があれば簡単にメモする
- ノートを閉じたら考えないと決める
書き出すことで脳に「これは明日考えればいい」と伝えることができます。
特に重要なことや締め切りのあることをメモすると、忘れる不安から解放されます。
頭の中で考えをぐるぐる回すより、紙に書き出す習慣をつけてみてくださいね。
就寝前のスマホやPC使用を控える
寝る前のスマホやパソコンの使用は、睡眠の質を低下させます。
デジタル機器から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、脳を覚醒状態に保つ作用があります。
スマホやPC使用を控えるための実践方法は以下の通りです。
- 就寝1〜2時間前にはデジタル機器の使用を終える
- ブルーライトカットフィルターを活用する
- 寝室にはスマホを持ち込まない
- 代わりに読書や瞑想などリラックスできる活動を行う
スマホの代わりに紙の本を読むなど、リラックスできる代替活動を見つけましょう。
また、睡眠アロマを活用するのもリラックス効果が期待できます。


夜はデジタルデトックスの時間と考えて、心と体をリラックスさせてくださいね。
入浴でリラックス効果を高める
入浴は身体的・精神的なリラックス効果があり、良質な睡眠を促します。
ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、体温調節機能が働き、自然な眠気を誘発する効果があります。
リラックス効果を高める入浴法は以下の通りです。
- 38〜40度のぬるめのお湯に20分程度浸かる
- 就寝の1〜2時間前に入浴する
- アロマオイルやバスソルトを活用する
- 入浴中は深い呼吸を意識する
入浴後、体温が下がっていく過程で眠気が生じます。
ただし熱すぎるお湯は交感神経を刺激するので、ぬるめの温度がおすすめです。
無理なく続けられる入浴習慣を見つけて、質の良い睡眠への準備をしましょう。
寝室の環境を快適な温度と湿度に調整する
快適な寝室環境は、良質な睡眠のための重要な要素です。
温度や湿度、明るさ、音などの環境要因は、寝つきや睡眠の質に直接影響します。
理想的な寝室環境を作るためのポイントは以下の通りです。
- 室温は16〜19度を目安にする
- 湿度は50〜60%程度を保つ
- 光が入らないようにカーテンを工夫する
- 静かな環境を確保する
季節に合わせた寝具選びも重要で、冷感ブランケットなどを活用するといいでしょう。
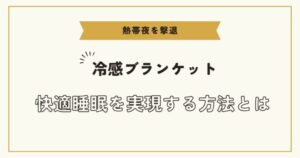
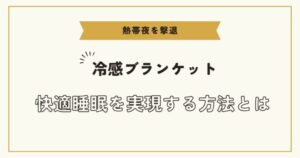
また、枕合わないと感じる場合は見直すことも重要です。


寝室は睡眠のための専用空間と考えて、快適な環境づくりを心がけましょうね。
「眠らなければ」という焦りから解放される
「早く眠らなければ」という焦りが、かえって寝つきを悪くすることがあります。
眠りへの執着や焦りは交感神経を活性化させ、リラックスした状態に入るのを妨げてしまうのです。
焦りから解放されるための考え方は次のようなものです。
- 一晩眠れなくても命に関わらない
- 横になるだけでも休息になる
- 「眠れない」と意識しすぎない
- 眠くなるまで無理に眠ろうとしない
眠れないときは本を読むなど、気分転換をしてみるのも良い方法です。
深い睡眠の理想な割合を追求するよりも、リラックスすることを優先しましょう。


焦りは睡眠の大敵、肩の力を抜いて過ごすことが大切ですよ。



眠れなくても焦らないで!リラックスが一番の睡眠薬です
更年期の寝つきの悪さに効果的な4つの対策
更年期には、ホルモンバランスの変化により睡眠トラブルが生じやすくなります。



更年期の睡眠問題は解決できます!
それぞれの対策について詳しく解説していきます。
ホルモンバランスを整える食事を摂る
更年期のホルモンバランスを整える食事は、睡眠の質向上に役立ちます。
女性ホルモンに似た働きをする植物性エストロゲンを含む食品や、トリプトファンを多く含む食品は睡眠の質を高める効果があります。
更年期の睡眠をサポートする食品には以下のようなものがあります。
- 大豆製品(豆腐、納豆、豆乳など)
- 亜麻仁油、えごま油
- バナナ、キウイなどのフルーツ
- カルシウムを多く含む乳製品
睡眠の質を上げる食べ物を積極的に取り入れましょう。
食事は消化の良いものを選び、就寝の2〜3時間前には済ませることが理想的です。
バランスの良い食事と規則正しい食事時間が、良質な睡眠につながりますよ。
就寝2時間前の軽い運動で体温調節を促す
適度な運動は睡眠の質を向上させる効果があります。
特に更年期には、ホットフラッシュなどで体温調節が難しくなることがあるため、軽い運動で体温の上昇と下降のリズムを整えることが重要です。
更年期におすすめの運動には次のようなものがあります。
- ウォーキング
- ストレッチ
- ヨガ
- 軽い筋トレ
就寝の2時間前に軽い運動を行うと、その後体温が下がっていく過程で眠気が促されます。
ただし、寝る直前の激しい運動は交感神経を刺激するので避けましょう。
自分のペースで無理なく続けられる運動習慣を見つけることが大切です。
寝具やパジャマの素材を見直す
更年期には寝汗や体温調節の問題が生じやすいため、寝具の素材選びが重要です。
吸湿性や放湿性に優れた素材を選ぶことで、快適な睡眠環境を作ることができます。
更年期におすすめの寝具素材には以下のようなものがあります。
- 綿や麻などの天然素材
- 吸湿性の高いシルク
- 温度調節機能のある機能性素材
- 通気性の良いメッシュ素材
特にシルクの枕カバーはさらっとした肌触りで快適です。


季節に合わせて寝具を調整し、快適な睡眠環境を整えるようにしましょう。
医師に相談して適切な治療を検討する
更年期の睡眠障害が生活に支障をきたす場合は、医師に相談することが大切です。
専門医による適切な診断と治療によって、症状の緩和が期待できます。
医師に相談する際のポイントは以下の通りです。
- 睡眠の状態を詳しくメモしておく
- 他の更年期症状も伝える
- 服用中の薬がある場合は伝える
- 生活習慣についても相談する
医師の判断により、ホルモン補充療法や睡眠薬の処方が検討されることもあります。
また、睡眠サプリについても医師に相談すると安心です。
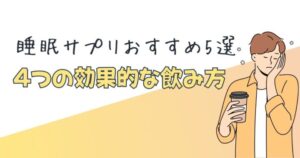
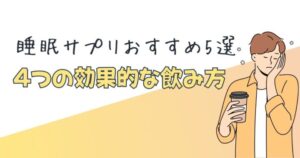
自己判断せず、専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な対策ができますよ。
眠れない夜に試したいツボ押し3選
眠れない夜には、東洋医学のツボ押しが効果的な場合があります。



ツボ押しで自然な眠気を誘発しましょう!
それぞれのツボについて詳しく解説します。
足裏のかかと中央にある失眠穴を刺激する
失眠穴(しつみんけつ)は、不眠の改善に効果があるとされるツボです。
足裏のかかとの中央にあるこのツボは、高ぶった神経を鎮め、リラックス効果をもたらします。
失眠穴の刺激方法は以下の通りです。
- 椅子に座り、片方の足首を反対側の膝の上に置く
- 親指でかかとの中央にある窪みを見つける
- 軽く押しながら20回程度たたく
- 両足交互に行う
失眠穴を刺激すると、気持ちが落ち着き、自然な眠気を誘発します。
両膝を立ててかかとを布団にすりつけるように刺激する方法もあります。
寝る前の習慣として取り入れると、リラックス効果が高まりますよ。
おへその下3〜5cmの丹田に手を当てる
丹田(たんでん)は、東洋医学で気の集まる重要なポイントとされるツボです。
おへその下3〜5cmほどの位置にあり、呼吸とともに意識を集中させることで、心身のバランスを整える効果があります。
丹田への意識集中方法は以下の通りです。
- あぐらをかいて座る
- 両手を重ねて丹田の上に置く(女性は右手が下、男性は左手が下)
- 目を閉じて丹田に意識を集中させる
- ゆっくりと深い呼吸を繰り返す
丹田に意識を集中させると、興奮した気持ちが落ち着いてきます。
腹式呼吸と組み合わせることで、さらにリラックス効果が高まります。
ベッドに入る前に数分間行うと、安らかな眠りにつきやすくなりますよ。
頭頂部の百会を優しく押して気持ちを落ち着ける
百会(ひゃくえ)は頭のてっぺんにあるツボで、精神を安定させる効果があります。
東洋医学では「百病を治す」とも言われ、特に心の落ち着きに関わるツボとして知られています。
百会のツボ押し方法は以下の通りです。
- 頭頂部の正中線上にあるツボを見つける
- 4本の指か手のひらを使ってやさしく押す
- 息を吐きながら5秒程度押す
- 軽く息を吸い、これを数回繰り返す
百会を刺激すると、頭がすっきりして気持ちが落ち着きます。
就寝前の気分の高ぶりを鎮めるのに効果的です。
力を入れすぎず、気持ちよく感じる程度の力加減で行うことがポイントですよ。



ツボ押しは日常に取り入れやすいので試してみて!
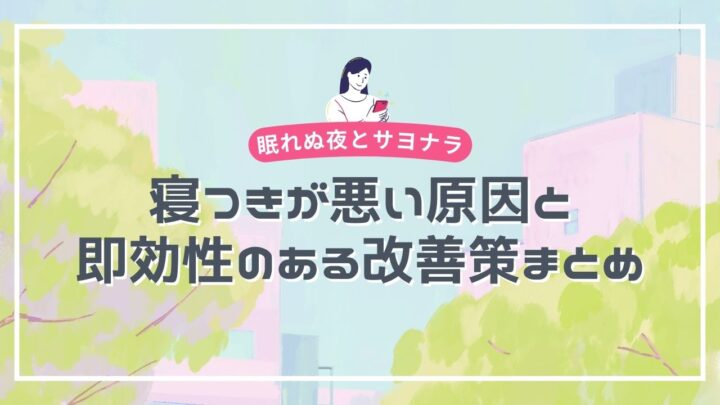
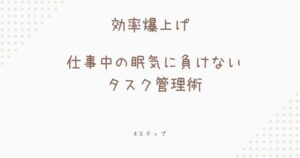



コメント